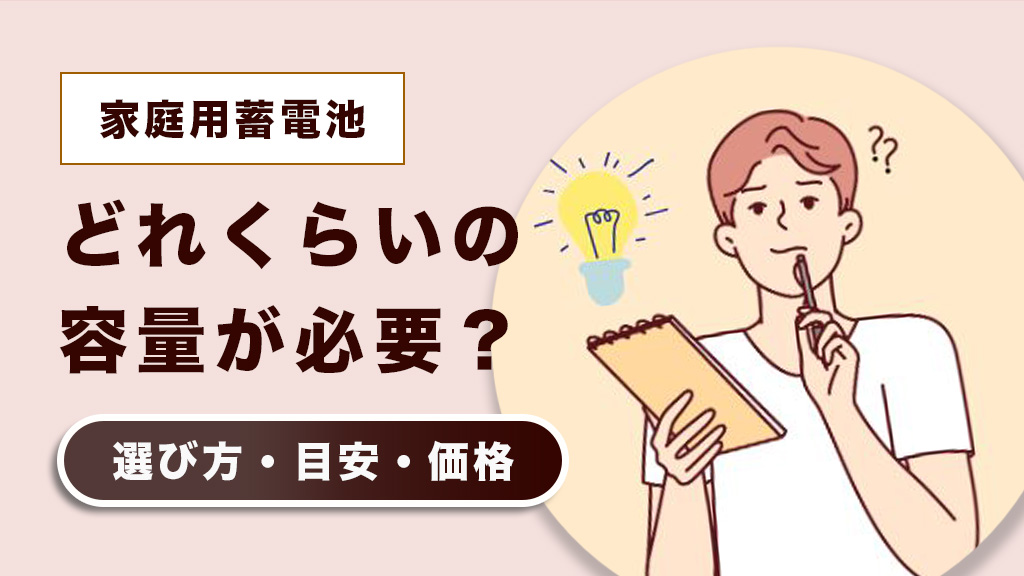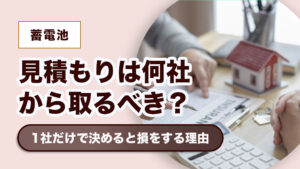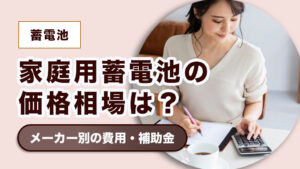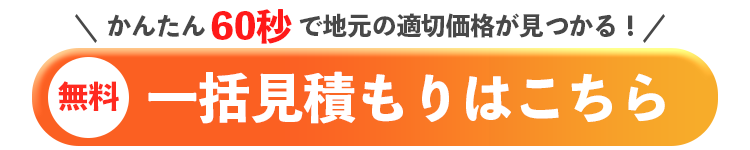蓄電池って、何kWhを選べばいいの?
容量が小さすぎても不安だし、大きすぎると高そう…。
蓄電池の容量は世帯人数や住宅タイプだけで一律に決めるものではなく、夜間や停電時にどれくらいの電気を使いたいかを基準に考えることが重要です。
一般的な目安としては、1〜2人暮らしなら4〜6kWh、4人家族なら6〜10kWh、オール電化住宅では10kWh以上がひとつの基準になりますが、実際には在宅時間や電気の使い方によって最適な容量は変わります。
この記事では、蓄電池の容量に関する基本的な考え方から、家庭別の容量目安、実際に使える家電のイメージ、価格や補助金まで分かりやすく解説します。

「自分の家には何kWhが適切なのか」を判断する参考にしてみてください。
今すぐ、
かんたん無料一括見積もりを
しましょう!
- ❶見積もり
情報を入力 - ❷料金・サービスを
比較 - ❸施工業者
決定
かんたん3ステップで
すぐに業者が見つかります!
蓄電池の「容量」とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

蓄電池の容量とは、どれだけの電気を蓄え、どのくらいの時間使えるかを示す指標です。
容量は「kWh(キロワットアワー)」で表され、数値が大きいほど長時間の電力供給が可能になります。ただし、カタログ上の数値どおりすべての電気を使えるわけではありません。
実際にどれくらい使えるかを正しく判断するためには、容量の表示方法の違いを理解しておくことが重要です。
定格容量と実効容量の違い
蓄電池の容量には、「定格容量」と「実効容量」という2つの考え方があります。
定格容量は、蓄電池が理論上蓄えられる最大量を示した数値です。一方、実効容量は、安全性や電池劣化を防ぐための制御を考慮した、実際に使用できる容量を指します。
| 項目 | 定格容量 | 実効容量 |
|---|---|---|
| 意味 | 理論上蓄えられる最大容量 | 実際に使える容量 |
| 数値の傾向 | カタログ表記そのまま | 定格容量よりやや小さい |
| 見るべきポイント | 性能比較の目安 | 生活で使える電力量の判断材料 |
容量(kWh)は「どれくらいの時間使えるか」を示す指標であり、同時に使える家電の数には出力(kW)も影響します。ただし、容量選びの段階では、まず必要なkWhの目安を把握することが重要です。
今すぐ、
かんたん無料一括見積もりを
しましょう!
- ❶見積もり
情報を入力 - ❷料金・サービスを
比較 - ❸施工業者
決定
かんたん3ステップで
すぐに業者が見つかります!
家庭用蓄電池に必要な容量の目安は?

家庭用蓄電池の容量目安は、1〜2人暮らしで4〜6kWh、4人家族で6〜10kWh、オール電化住宅では10kWh以上がひとつの基準になります。
ただし、最適な容量は世帯人数だけで決まるものではなく、在宅時間・電気の使い方・太陽光発電の有無によって大きく変わります。
ここでは、家庭用蓄電池に必要な容量の目安を具体的に解説します。
1~2人暮らし
1〜2人暮らしの世帯では、使用する家電が比較的少なく、電力消費も安定しやすいため、小〜中容量の蓄電池でも十分対応できるケースが多いです。
4kWh〜6kWh
日中は外出している時間が長く、夜間の電力使用が中心となる共働き世帯であれば、4〜6kWh程度の実効容量で電力を十分にまかなえることが一般的です。
また、停電時に冷蔵庫・照明・通信機器など最低限の家電を動かす目的であれば、小容量でも安心感を得られます。
| 使用家電 | 消費電力量の目安 | 稼働時間(目安) |
|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 約0.2kWh/h | 約20〜25時間 |
| LED照明(複数) | 約0.1kWh/h | 約40時間 |
| テレビ | 約0.15kWh/h | 約25時間 |
在宅時間が長い方や、冷暖房を日常的に使用する場合は、6kWh前後まで容量を持たせておくと安心です。
4人家族
4人家族になると、朝夕に調理・洗濯・冷暖房が重なり、電力使用が集中する時間帯が増える傾向があります。
6kWh〜10kWh
この容量帯であれば、日常の自家消費に加えて、停電時でも数時間〜半日程度の電力確保が可能になります。
特に子育て世帯では、冷暖房や調理家電を同時に使う場面も多いため、容量にある程度の余裕を持たせることで使い勝手が向上します。
同時に多くの家電を使う家庭では、容量だけでなく出力(kW)もあわせて確認しておくと安心です。
電気使用量が多い家庭(オール電化住宅)
オール電化住宅では、給湯・調理・冷暖房をすべて電気でまかなうため、一般住宅よりも電力消費量が多くなります。
10kWh〜13kWh以上
10kWh以上の容量があれば、高出力家電を使う環境でも、停電時の影響を最小限に抑えやすくなります。
また、オール電化住宅では容量だけでなく、実際にその電気を使える仕様かどうかも重要になります。
とくに、IHクッキングヒーターやエコキュートなどの200V機器を使用している場合は、200V対応の蓄電池かどうかを事前に確認しておきましょう。
【容量別】蓄電池で使える家電と稼働時間の目安

蓄電池の導入を検討する際、「実際にどの家電がどのくらい使えるのか」という具体的な目安があると安心です。
ここでは、5kWhと10kWhの蓄電池を例に、稼働可能な家電とその時間の目安を詳しく紹介します。
また、生活スタイルに合わせて必要な容量がどう変わるのかもシミュレーションしてみましょう。
5kWhでどんな家電がどれくらい使える?
5kWhの蓄電池は、比較的小規模な家庭や、停電対策を目的とした非常用電源として選ばれることが多い容量です。
この容量があれば、冷蔵庫や照明、テレビといった最低限の家電は数時間から十数時間にわたって稼働させることができます。
また、在宅時間が短い共働き世帯などには特に適した容量といえるでしょう。
以下に、5kWhの蓄電池で稼働可能な家電と、各機器の使用時間の目安を表にまとめました。
| 家電製品 | 消費電力の目安(W) | 稼働時間の目安(5kWh) |
|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 約50W | 約100時間 |
| 液晶テレビ | 約100W | 約50時間 |
| LED照明(2部屋分) | 約80W | 約62時間 |
| 携帯電話充電器 | 約15W | 約333時間 |
| ノートパソコン | 約100W | 約50時間 |
| 炊飯器 | 約150W | 約33時間 |
| エアコン(弱運転) | 約500W | 約10時間 |
10kWhの蓄電池なら停電時も安心?
10kWhの蓄電池は、家族の多い家庭や、オール電化住宅などでの使用に適した容量です。
一般的な4人家族であれば、日常生活に必要な基本的な家電を一晩~1日程度稼働させることができ、停電時にも生活の質を大きく下げずに済みます。
10kWh以上の蓄電池であれば、エアコンやIHクッキングヒーターなど、消費電力の高い家電にもある程度対応可能です。
| 家電製品 | 消費電力の目安(W) | 稼働時間の目安(10kWh) |
|---|---|---|
| 冷蔵庫 | 約50W | 約200時間 |
| 液晶テレビ | 約100W | 約100時間 |
| LED照明(2部屋分) | 約80W | 約125時間 |
| 携帯電話充電器 | 約15W | 約666時間 |
| ノートパソコン | 約100W | 約100時間 |
| 炊飯器 | 約150W | 約66時間 |
| エアコン(弱運転) | 約500W | 約20時間 |
10kWh程度の蓄電池であれば、「1日分の最低限の生活電力を確保できる」というイメージです。
ご家庭にあった容量の選び方

蓄電池の容量選びは、「何kWhあれば足りるか」だけで判断すると失敗しがちです。
使用目的・日常の電気使用量・将来の生活変化・価格とのバランスを総合的に考えることで、自宅に合った容量を無理なく選ぶことができます。
ここでは、家庭用蓄電池の容量を選ぶうえで押さえておきたい4つのポイントを解説します。
使用目的(災害対策・節電・自家消費)を明確にする
蓄電池の容量を決めるうえで、最初に整理すべきなのが「何のために使うのか」という目的です。
- 災害対策:停電時でも冷蔵庫・照明・通信機器などを使えるようにする
- 節電:電気料金が高い時間帯の使用量を抑える
- 自家消費:太陽光発電の余剰電力をためて家庭内で使う
災害対策が目的であれば、最低限使いたい家電を動かせる容量があれば十分な場合もあります。
一方、日常の節電や太陽光発電の自家消費を重視する場合は、夜間に使う電力量をまかなえるだけの容量が必要になります。
日常的に使う電力量(kWh)を把握する
容量選びで重要なのは、「どの家電を、どれくらいの時間使いたいか」を把握することです。
夜間や停電時に使いたい電力量の合計が、必要な蓄電池容量の下限と考えると分かりやすくなります。
- 家電の消費電力(W)を確認する
- 使用時間(h)をかける
- 1000で割ってkWhに換算する
この合計値に少し余裕を持たせた容量を選ぶことで、無理のない運用ができます。
将来の電力使用増加も見据えて選ぶ
現在の電力使用量だけでなく、今後の生活変化も想定して容量を選ぶことが大切です。
- 家族が増える・在宅時間が長くなる
- 在宅ワークの導入
- オール電化住宅への切り替え
- 電気自動車(EV)の導入
将来的に電気使用量が増える可能性がある場合は、初めからやや余裕のある容量を選んでおくと、後悔しにくくなります。
価格と容量のバランスを見極める
蓄電池は容量が大きくなるほど価格も上がるため、必要以上に大容量を選ぶとコスト負担が大きくなります。
一方で、容量が不足すると本来の目的を果たせません。
「どこまでの電力をまかないたいか」と「予算」のバランスを考えながら、最適な容量を選ぶことが重要です。
次の章では、容量別に実際に使える家電と稼働時間の目安を具体的に解説します。
容量別の蓄電池価格相場

家庭用蓄電池の価格は、容量(kWh)が大きいほど上がります。ただし、同じ容量でも価格差が出るため、「容量」だけでなく「本体+工事費+保証」を含めた総額で比較することが大切です。
ここでは、容量帯ごとの価格目安を整理しつつ、金額が変わりやすいポイントも合わせて解説します。
- 1〜5kWh:約90万〜150万円前後
- 5〜10kWh:約140万〜200万円前後
- 10kWh以上:約180万〜260万円前後
※目安は製品や工事条件で変わります。見積もりでは「工事費」「保証」「追加工事の有無」を必ず確認してください。
1~5kWhのコンパクトモデル
1〜5kWhは、導入コストを抑えたい場合に選ばれやすい容量帯です。価格は約90万〜150万円前後が目安になります。
機種によっては本体が安く見えても、分電盤まわりの作業や設置条件で工事費が上がることがあります。見積もりでは、本体価格と工事費が分けて記載されているかをチェックしてください
5~10kWhの中容量帯モデル
5〜10kWhは、価格と容量のバランスが取りやすい容量帯です。価格は約140万〜200万円前後が目安になります。
このゾーンは製品ラインナップが多く、同じ容量でも保証年数や制御方式の違いで総額が変わります。比較する際は、実効容量・保証内容・工事費込みの総額を同じ条件にそろえて判断しましょう。
10kWh以上の大容量モデル
10kWh以上は、容量をしっかり確保したい場合に選ばれます。価格は約180万〜260万円前後が目安です。
この容量帯は本体価格が上がりやすい一方で、容量が増えるほど1kWhあたりの単価が下がる傾向もあります。初期費用だけでなく、停電対策や自家消費の考え方と合わせて選ぶと失敗しにくくなります。
補助金制度を活用してお得に蓄電池を導入

家庭用蓄電池は高額な設備ですが、国や自治体の補助金制度を活用することで、実質負担を大きく抑えられる場合があります。
補助金は年度や地域によって内容が異なるため、制度の全体像を把握した上で、自宅が対象になるかを確認することが重要です。
国の補助金制度
国が実施している補助制度には、再生可能エネルギーの普及や電力需給の安定化を目的としたものがあります。
- DR(デマンドレスポンス)対応蓄電池向け補助
- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業
- 子育て世帯・若年世帯向け住宅支援制度
たとえばDR関連の補助制度では、一定の条件を満たす蓄電池に対して、1kWhあたり数万円規模、上限数十万円程度の補助が設定される年があります。
また、ZEH支援事業では住宅全体の省エネ性能が評価対象となり、条件を満たすことで数十万円〜100万円規模の補助が用意されるケースもあります。蓄電池は上乗せ補助の対象になる場合があり、新築や大規模リフォーム時に検討されることが多い制度です。
これらの制度は年度ごとに内容や補助額が見直されるため、申請前に必ず最新の公表情報を確認してください。
自治体ごとの支援金・助成金
国の制度に加えて、多くの自治体でも家庭用蓄電池の導入を支援する補助金や助成金が用意されています。
自治体補助は国の補助金と併用できる場合もあり、実質負担をさらに抑えられる点が大きなメリットです。
- 地域ごとに補助額や条件が大きく異なる
- 容量や設置方法に応じて補助額が変わる場合がある
- 太陽光発電との同時導入で条件が優遇されることもある
たとえば都市部では、容量に応じて数十万円〜100万円前後の補助が設定される年もあり、全国的に見ても支援額が手厚い傾向があります。
一方で、地方自治体でも上限5万〜20万円程度の補助を実施しているケースがあり、太陽光発電との併用が条件になることもあります。
補助金を活用する際の注意点
補助金制度を確実に活用するためには、いくつか押さえておきたい注意点があります。
- 申請期間と予算上限の有無
- 対象となる蓄電池の性能・認証条件
- 国と自治体補助の併用可否
- 契約・設置前後の申請タイミング
補助金は工事完了後では申請できない制度も多く、契約や着工のタイミングを誤ると対象外になることがあります。
また、必要書類が多く、不備があると不受理になるケースもあるため、補助金申請の実績がある施工業者に相談すると安心です。
蓄電池の容量に関するよくある質問

蓄電池の容量に関して多くの方が疑問に思うことをまとめました。
- Q蓄電池の容量はどのように計算すればいいですか?
- A
蓄電池の容量は「夜間や停電時に使いたい電力量」を基準に計算します。
具体的には、使いたい家電の消費電力(W)に使用時間(h)を掛け、合計をkWhに換算します。たとえば、冷蔵庫0.2kWh、照明0.3kWh、テレビ0.5kWhを夜間に使う場合、合計で約1.0kWhになります。
この合計値を目安に、余裕を持たせた容量を選ぶと、実際の使用時に不足を感じにくくなります。
- Q容量の違いで充電や放電の速度は変わりますか?
- A
容量そのものは「蓄えられる量」を示す指標であり、充電や放電の速度(=出力)は「出力kW」の値によって決まります。
たとえば10kWhの蓄電池でも、出力が2kWであれば一度に使える電力は2kWまでです。
容量と出力は別の指標なので、併せて確認しましょう。
- Q複数の蓄電池を組み合わせて容量を増やすことはできますか?
- A
一部のメーカーでは、同一機種の蓄電池を2台以上設置して、容量を拡張できるシステムが提供されています。
- Q容量が劣化すると使える電力量も減りますか?
- A
はい、使用年数や充放電の繰り返しによって蓄電池の容量は徐々に劣化し、実効容量も減少します。
製品によっては10年後に約70〜80%程度に低下するのが一般的です。
- Q蓄電池の容量表示に「Ah(アンペアアワー)」が使われることがありますが、kWhとどう違うのですか?
- A
Ah(アンペアアワー)は電流量を基にした容量表示で、電圧(V)との組み合わせでkWhに換算されます。
家庭用では「kWh」で表記されることが一般的なので、製品比較時は単位を揃えて確認するようにしましょう。
- Q容量が大きい蓄電池は停電時にエアコンやIHクッキングヒーターも使えますか?
- A
停電時にこれらの高出力家電を使えるかどうかは、容量だけでなく「出力」と「分電盤接続方式(特定負荷型・全負荷型)」にもよります。
容量が十分でも、出力が小さいと稼働できない場合があります。
特にIHや200Vエアコンを使いたい場合は、200V対応・全負荷型かを事前に確認しましょう。
蓄電池の容量まとめ

蓄電池の容量選びは、家庭での電気の使い方やライフスタイルに合わせて最適なものを選ぶことが重要です。
5kWh程度の小容量モデルは1〜2人暮らしや最低限の停電対策に、10kWh前後の中容量モデルは標準的な4人家族に、そして10kWh以上の大容量モデルはオール電化住宅や電気自動車を所有する家庭に適しています。
選び方のポイントは、以下の通りです。
- 使用目的を明確にする: 災害対策なのか、電気代節約なのか、太陽光発電との組み合わせなのかを考慮
- 電力使用量を把握する: 現在の電気使用量と必要な家電の消費電力を確認
- 容量と出力の違いを理解する: kWh(容量)とkW(出力)は異なる概念で、両方が重要
- 将来の使い方も考慮する: 家族構成の変化やEV導入など、将来の電力需要増加も視野に入れる
- 価格と容量のバランスを考える: 1kWhあたりの単価を比較し、コストパフォーマンスを検討
- 補助金制度を活用する: 国や自治体の補助金を利用して導入コストを抑える
適切な容量の蓄電池を選ぶことで、災害時の安心や電気代の節約につながります。
相見積もりを取ってより安く信頼できる業者へ依頼するのがおすすめ
一括見積もりサイトを利用すれば、1回の入力で複数業者の見積もりが届くため、総額・保証・工事内容の違いを効率的に確認できます。
とくに「エコ×エネの相談窓口」は、最短60秒で蓄電池の相見積もりが取れるサービスで、以下のような安心ポイントが特徴です。

- 優良業者のみ登録
口コミ・紹介・リピーター中心の信頼できる販売施工会社だけを厳選 - 「イエローカード制度」で悪質業者を排除
評判が悪い・クレームが多い業者は契約解除の対象に - 販売施工会社への断りも代行対応
「断りづらい…」という方のために、当社が代行連絡をサポート
しつこい営業がなく、価格・保証・施工内容をまとめて比較できるため、初めて蓄電池を導入する人でも安心して利用できます。蓄電池の交換を希望する場合は、見積もり依頼時に「蓄電池の交換希望」と明記しておくとスムーズです。
今すぐ、
かんたん無料一括見積もりを
しましょう!
- ❶見積もり
情報を入力 - ❷料金・サービスを
比較 - ❸施工業者
決定
かんたん3ステップで
すぐに業者が見つかります!